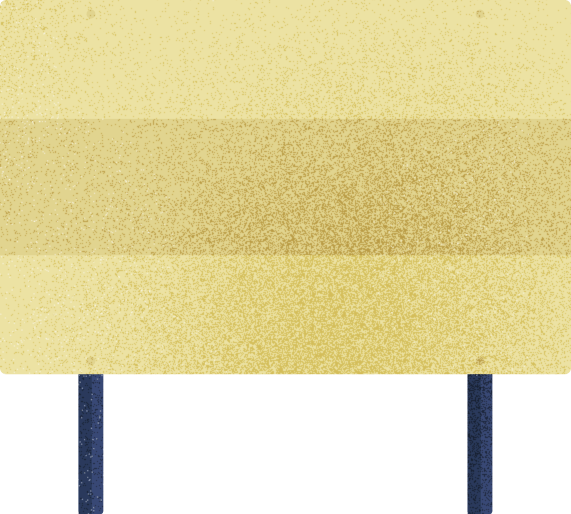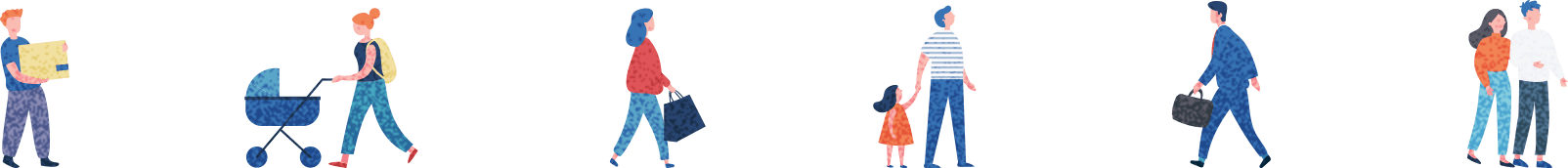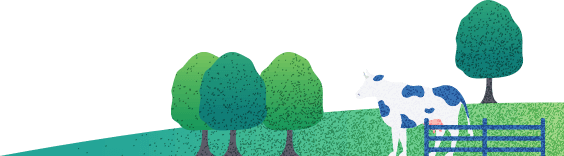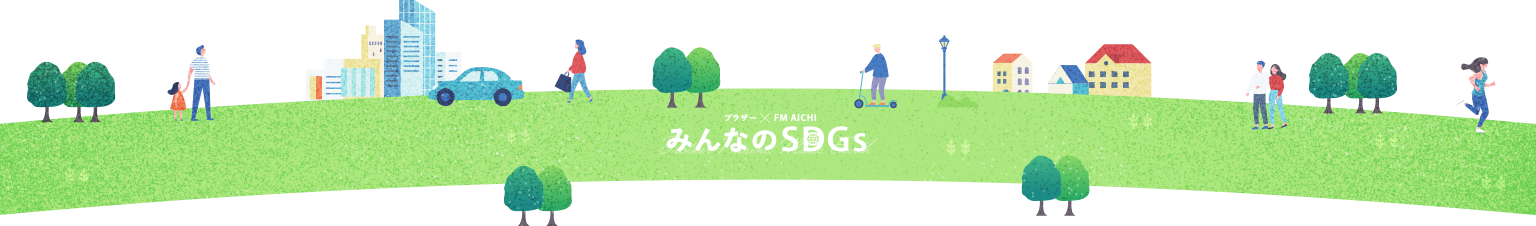
現在世界の人口はおよそ77億人。2050年には97億人になるとの予想もあります。
そこで問題になるのは、食糧の確保。その対策のひとつとして注目を集めているのが、「昆虫食」。中でも「食用コオロギ」の生産に取り組んでいる、株式会社グリラスの代表取締役CEO 渡邉 崇人さんにお話しをうかがいました。
タンパク源として注目される昆虫

食用コオロギについて語る渡邉さん
2020年に、無印良品が発売して話題になった「コオロギ入りのせんべい」に、食用コオロギを提供しました。食用コオロギを乾燥させ、粉末にして練り込んであるんですが、エビせんべいのような香ばしさでおいしいと感想をいただいています。
地球上の人口はどんどん増え続けており、これからますますタンパク質の供給が求められます。タンパク源はこれまでは牛や豚、鶏などの肉類で供給するのが通常でしたが、これだと効率が悪い。1キロの肉をつくるのに、めちゃくちゃたくさんのエサがいりますよね。しかも、そのエサを増やすのが難しくなっています。そこで、より効率のよいタンパク源として昆虫が注目されているんです。
なぜコオロギなのか?

コオロギの粉末使ったクッキーとプロテイン
イナゴやハチノコといった伝統的な昆虫食もありますが、これらは養殖ができないんですね。食糧問題への対策として考えると、コオロギは「養殖できる」ということが、最大の特性です。実は、昆虫って食べるものが偏っているものが多いんです。例えば、カイコは桑しか食べない、とかね。しかしコオロギは雑食なので、エサに困りません。我々も今、コオロギの養殖には食品残渣などを使っていて、食品ロス削減につなげています。
それに、コオロギは成長が早いんです。卵から食用に成長するまでにおよそ1か月。年に10回から11回も出荷できるというところも利点ですね。
栄養面からすると、4分の3くらいがタンパク質。かなりプロテインがリッチな食材ですし、その他にも食物繊維やビタミン、ミネラルなども多く含まれています。
味はよく「エビのような」という表現がされますが、実は、エサによって味のコントロールが結構可能なんです。我々も、おいしくなるようにエサをいろいろ検討しています。
小さなコオロギが大きな地球を救う

徳島県・美馬市の廃校を利用した研究所
もともと徳島大学では30年近くコオロギの基礎研究が行われていました。わたしもそこで16年、研究に携わってきましたが、「コオロギを研究して何の役にたつの?」となかなか社会から理解されることが少なかったんです(笑)研究自体はおもしろく、コオロギをなんとか直接社会の役にたてる方法はないものか?とずっと考えていたことが、食用コオロギの養殖につながりました。一口にコオロギといっても種類がたくさんあるのですが、研究の結果、食用に適していると判断し養殖しているのは、「フタホシコオロギ」という品種です。社名の「グリラス」はフタホシコオロギの学名です。
コオロギせんべいの他にも、自社ブランドをたちあげてクッキーやチョコクランチ、カレーやパンにコオロギの粉末を使った商品を展開しています。コオロギの味を感じさせながら、おいしい商品になっていますのでぜひ味わってみて下さい。
現在、徳島県の美馬市で廃校を利用して食用コオロギを量産するシステムの研究を行っています。将来的には、全国にコオロギの生産拠点を築くだけでなく、飢餓に直面している中東やアフリカなどの地域にもコオロギのタンパクを運んでいけるような流通網も整えたいと考えています。
株式会社グリラス 代表取締役CEO
渡邉 崇人さん


この取り組みのSDGsを知ろう
「すぐわかるSDGs」では、SDGsの17の目標をイラスト付きで分かりやすく解説しています。気になるゴールを押すと、目標の解説を1分程度で読むことができます。この記事に登場したSDGsを見てみましょう。

Brother presents Music Earth
今、世界では温暖化、貧困、格差社会…様々な地球規模の課題があります。
これからの「地球」の為に、今、私たちにできる事は一体何なのでしょうか?

毎週月曜 19:30 -19:55
FM AICHIにて放送中