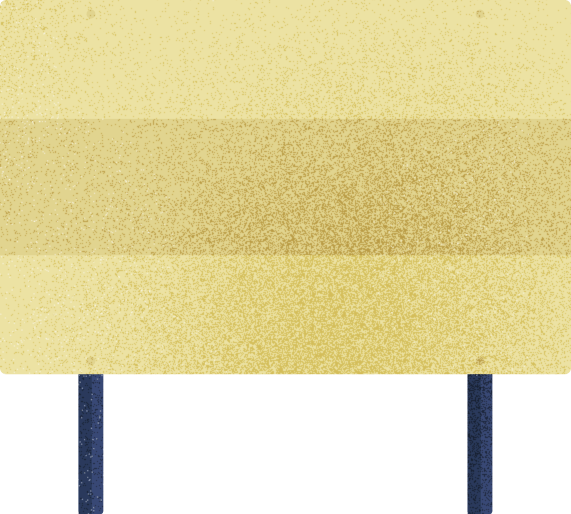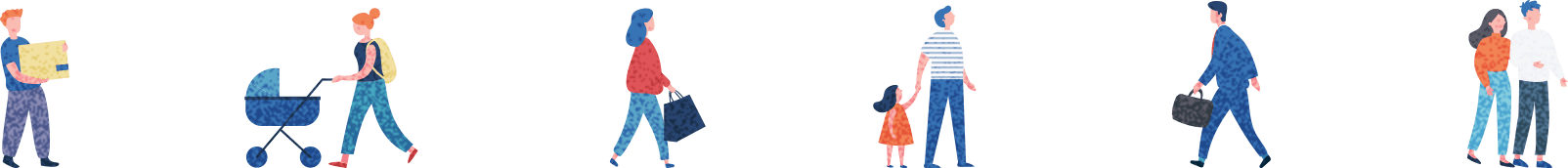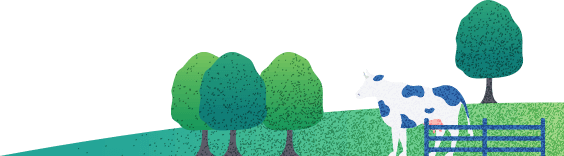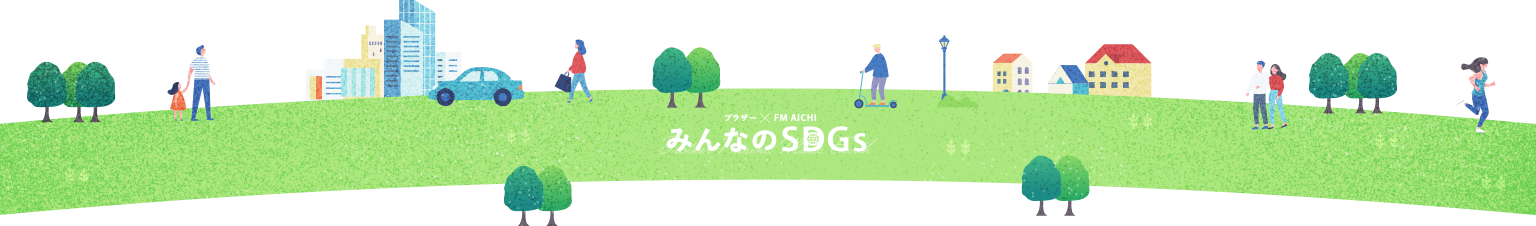
街の中でミツバチを飼育してはちみつを採る、都市養蜂。ミツバチを通じて足元の環境を考えてもらおうと、2022年9月に「親子ミツバチ見学会」が、名古屋市中区長者町で開かれました。番組では2週にわたってそのイベントの様子と都市養蜂の意義について、リポートを届けました。
初めての親子ミツバチ見学会

名古屋で都市養蜂を行っている「マルハチ・プロジェクト」と東京の「銀座ミツバチプロジェクト」が初めて共同で開催。12組31人の親子が集まりました。まずは、「マルハチ・プロジェクト」が長者町のビルの屋上で飼育しているミツバチの巣箱を、皆で見学。網付きの麦わら帽子をかぶって、おそるおそる巣箱をのぞき込む子どもたち。「このひと枠に2000匹はいるんだよ」「ほら、今、おしりをいれて卵産んだのが女王バチだよ!」と主催のひとりで全国の都市養蜂のリーダー的存在でもある「銀座ミツバチプロジェクト」副理事長の田中淳夫さんが、楽しく案内。初めて巣箱を目にした子どもたちだけでなく、親たちも興味津々。ついには、「ここ(巣)に直に指をつっこんで、はちみつなめてみよう!」ということに。その味の濃さに皆目を丸くしていました。
ミツバチの生態を知ろう

巣箱をみせる松良さん
屋上での巣箱の観察の後は、近くの会場でミツバチの生態について、名古屋の「マルハチ・プロジェクト」の代表理事 松良宗夫さんがやさしく解説。ミツバチが一生に集められるはちみつは、ティースプーン1杯にも満たないこと。ミツバチが蜜を集めてくる範囲は3キロ四方であること、ミツバチが花粉を運ぶことによって、果実が実ることなど、自然界での役割について親子で学ぶ機会になりました。「どうして蜂は黒いものを攻撃するといわれているのか?」「女王バチはどうして生まれるのか」など鋭い質問も子どもたちから飛び出しました。また、長者町だけでない、名古屋市内の別の場所でとれたはちみつや、銀座でのはちみつなどとの食べ比べも行い、季節や場所によってはちみつの味が違うことも実感。参加した親子からおどろきの声があがりました。
ミツバチが教えてくれるもの

「動画や写真などで観ていたミツバチとは違い、やはり、本物に触れることの大切さを感じました」「ミツバチと人間の関係の大切さを改めて実感しました」と見学会は、子どもたちの笑顔と大人たちの興奮のうちに終了。
「環境というものを、机の上で学ぶんじゃなくて、リアルに生き物を見て、感じる、ああいうのが、都会の子どもたちにもやっぱり必要なんじゃないかと思うんですよね」と主催の田中さんと松良さん。子どもたちから活発な質問が出たことにも手ごたえを感じたそうです。子どもたちはこれから気候変動の影響とかをもろにうけるじゃないですか。そういう環境の変化の中で、自分たちがどう生きていくのか。そういうことに真剣に思いを馳せているんだと思います。また、ミツバチを通して足元の環境を知るということもありますが、受粉媒介するミツバチは、人と人もどんどん結んでいくんですよね。「親子見学会」は、東京・大阪・名古屋と今回初めて3都市で行いましたが、この反響をうけて、全国のプロジェクトの仲間たちとつながっていければと思います。
銀座ミツバチプロジェクト&マルハチ・プロジェクトさん


この取り組みのSDGsを知ろう
「すぐわかるSDGs」では、SDGsの17の目標をイラスト付きで分かりやすく解説しています。気になるゴールを押すと、目標の解説を1分程度で読むことができます。この記事に登場したSDGsを見てみましょう。

Brother presents Music Earth
今、世界では温暖化、貧困、格差社会…様々な地球規模の課題があります。
これからの「地球」の為に、今、私たちにできる事は一体何なのでしょうか?

毎週月曜 19:30 -19:55
FM AICHIにて放送中