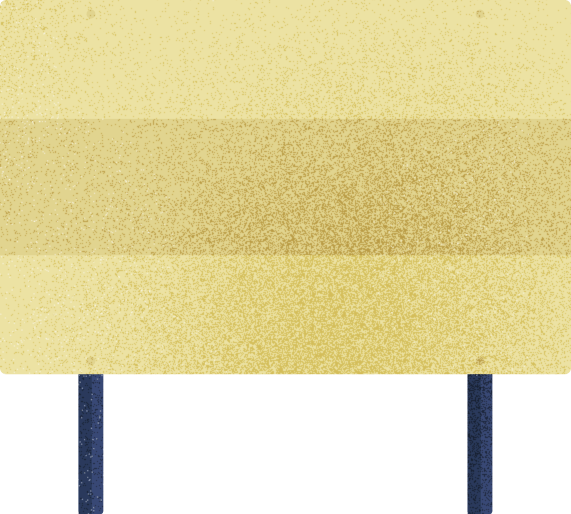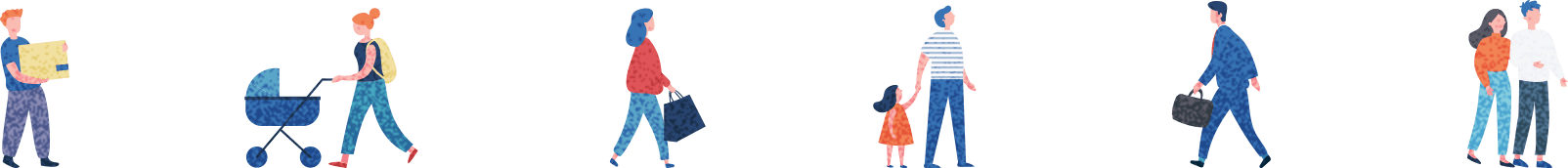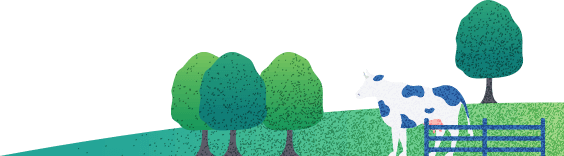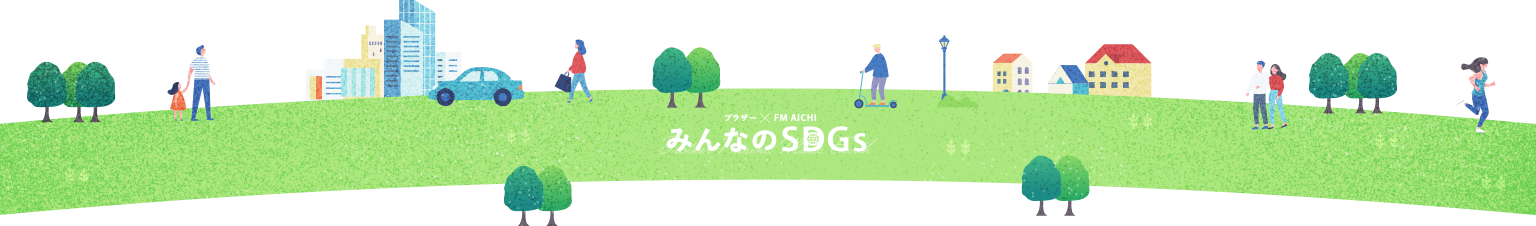
岐阜県郡上市にあるブラザーの森。かつてはスキー場だった荒れた森を再生しようと
ブラザーと岐阜県、郡上市が連携して、2008年から植樹活動が始まりました。しかし、植樹した木がなかなか育たないという問題が発生。専門家たちのサポートを経て、新たに見えてきた森の姿とは…? 森づくりのサポートに入っている名古屋大学大学院環境学研究科 高野 雅夫教授にお話をうかがいました。
植えた木の6割が枯れていた

もともとは「森を育てて、二酸化炭素を吸収してもらおう」という目的で、植樹活動がスタートしたと聞いています。2008年から毎年2回、ブラザーの社員の方たちが100人近く参加して植樹を続けているのに、植えた木がなかなか育っていない。専門的な見地から、この森が育っているのかどうか調査してほしいと相談をうけました。2014年のことです。そこで、動植物、土壌などの専門の先生方とチームをつくって調査にはいったところ、植えた木の4割くらいしか生き残っていなかったことがわかりました。普通スギの木の植林だと9割くらいは生き残るんです。この森では広葉樹を植えていますが、広葉樹の植林は針葉樹より難しいといわれています。森の再生のためには、もう少し成果をあげていくために植樹計画を見直すことになりました。
エリアごとに異なる木を植える

まず、土壌の調査をしてもらいました。木というのは水分が好きな木とあまり好きじゃない木があるんですね。また自然に生えている草も調査すると、場所ごとに生えている植物の種類が違うということもわかってきました。草原のような明るい乾燥した場所に生える草が沢山いるエリア、土壌にかなり水分が多くて湿地のようなところが好きな植物が生えているエリア、そして、いわゆる木が育ちやすい木陰を好む植物が暮らすエリア。今までの植樹はそういうところがわからずに、どこにでも同じ様な木を同じ様に植えていたんですね。樹木が育ちやすいところに重点的に植樹をし、育ちにくいところはむしろ草原のようなエリアとして維持していく、水分の多いエリアには水の好きな木を植えていくといったやり方にしていこうと。「ゾーニング」と言いますが、場所ごとに植える樹種を変えていくことにしました。
しかし、すぐに結果が出るわけではないです。いわゆる「どんぐり」の落葉広葉樹を中心に植えているんですが、苗を植えたあとの土がしっかり固まらずに倒れたり、夏場の草の成長に負けてしまったり。それに郡上は雪が多いですからね。雪の重みで苗木が倒れてしまうんです。雪に埋もれても強い樹種ということで「ブナ」も植えるようにしています。また、2008年からの植樹で生きのこった樹種も調査でわかってきていますので、そうした樹種を中心に植樹を行うようにしました。
ブラザーの森が新たに目指すもの

動植物の調査から、ここには多様な蝶が生息していることもわかってきました。特に貴重な「ギフチョウ」がこの森ではたくさん観察されています。草原と森林の中間のような場所を好む蝶ですが、木がぐんぐん育たなかったことが逆に功を奏したようです(笑)「森を大きく育てて二酸化炭素を吸収してもらおう」という当初の目的とは変わりますが、現在は、ギフチョウをはじめとする多様な生物が暮らせる環境を生かした森づくりを目指していこうと考えています。そうした多様な森を育て維持するためには、手入れが必要です。みなさんには植樹だけでなく、夏の下草刈りを手伝ってもらったり、植えた苗木の成長を我々と一緒に調査してもらったり。そうした活動の場所になることにも意義があると感じています。昔は生活の近くに人の手が入った森がある「里山」の暮らしがありましたが、現代では都会に暮らしていると、森は遠い存在になりがちです。森を一緒に育てる機会を楽しみながら、森を身近に感じてもらう。ブラザーの森はそんな役目を担ってくれる森になる可能性を秘めていると思います。
名古屋大学大学院環境学研究科 高野雅夫教授


この取り組みのSDGsを知ろう
「すぐわかるSDGs」では、SDGsの17の目標をイラスト付きで分かりやすく解説しています。気になるゴールを押すと、目標の解説を1分程度で読むことができます。この記事に登場したSDGsを見てみましょう。

Brother presents Music Earth
今、世界では温暖化、貧困、格差社会…様々な地球規模の課題があります。
これからの「地球」の為に、今、私たちにできる事は一体何なのでしょうか?

毎週月曜 19:30 -19:55
FM AICHIにて放送中