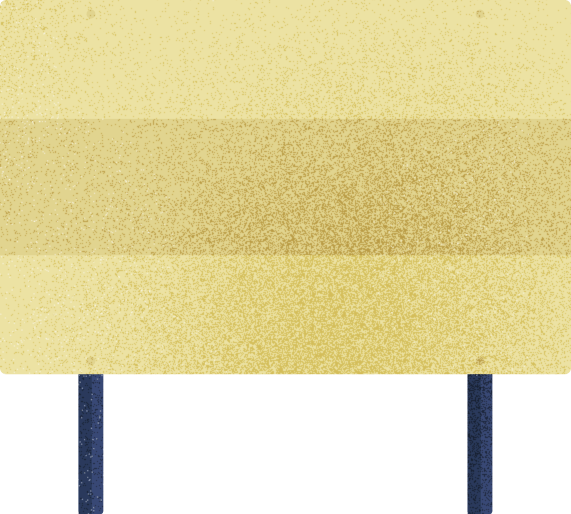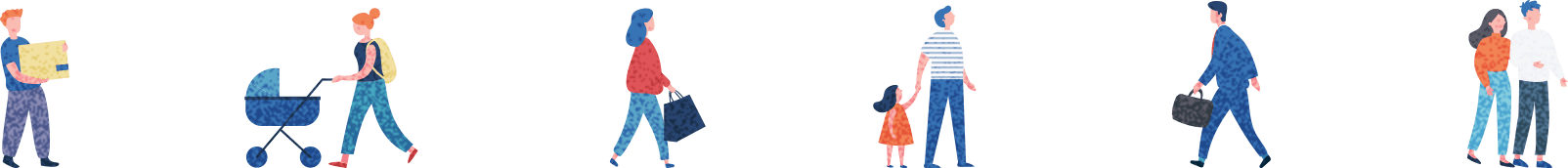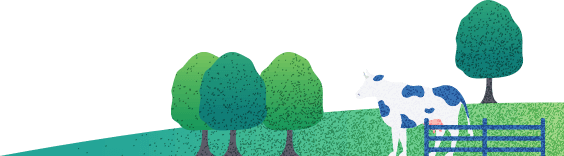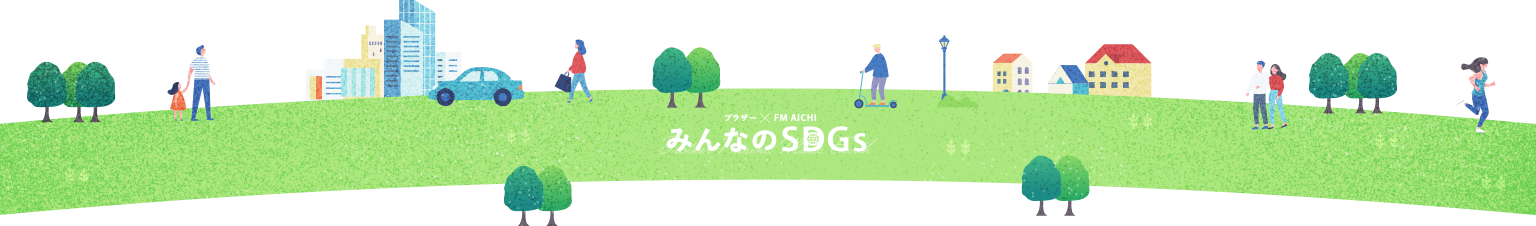
森が私たちの暮らしに一体どんな影響を与えているのか、そして守るためには私たちが何をしなくてはいけないのか?正確に答えられる人は、案外少ないのかもしれません。
そんな森の現状や未来について楽しく知って学ぼうというのが、今年(2023年)の3月にリリースされたばかりのカードゲーム「moritomirai(森と未来)」。
山梨日日新聞社 「moritomirai(森と未来)」事務局 藤井 聖二さんに、ゲーム開発のきっかけなど詳しくお話をうかがいました。
森を守ること=木を切らないこと という誤解

山梨日日新聞社では2021年7月から「山梨SDGsプロジェクト」を発足。県内のSDGs活動を推進する中でより具体的なアクションを起こしたいと、山梨県が抱える問題を洗い出し、「森」に注目しました。山梨県には日本で一番大きいSF認証の森(ちゃんと管理されて利用ができる)があり、また、森林率が全国の都道府県の中で第5位と森林がとても豊かなんです。また活動の一環で、「自分でできるSDGs」宣言を県民から募集。紙面に掲載しているんですが、その中に「木を切らないようにしよう」という宣言が多く寄せられることに気づきました。日本の木はすでに50年以上経っているものが多く、本当は「使って」「循環させていく」べきなんです。森に対するそのあたりの意識を、みなさんに変えてもらうきっかけづくりがまずは大切だと考えました。
森に対する正しい知識を身につけることから

楽しく森に対する知識を身につけてもらうには、「ゲーム」かな、と。ビジネスゲームを開発している株式会社プロダクトデザイン(富山県)と共同で開発にあたりました。「moritomirai(森と未来)」は、家庭で遊ぶカードゲームではなく、学校や講習会など大勢で学ぶためのツールです。10人以上(最大40人)で楽しむようになっています。プレイヤーは、山の持ち主、木を切る人、地域の会社のまとめ役(商工会のイメージ)、猟師・森を育てる団体の人、役所の人、学校の先生、販売会社の社員(木材を売る商社)、住宅メーカーの社員、新聞社やテレビ局の人、木材を加工する人、と10種類の役割にわかれて、シミュレーションしていく仕組みです。実際に森の中に入って仕事をする人たちはもちろん、そうでない人たちも森にかかわっているんだということもこの設定から伝わると思います。役割に紐づいて「仕事のカード(それぞれの仕事特有のもの)」と「生活のカード(仕事に関係なくダブるものも)」があって、それぞれがどんな行い(カードを切る)をするかによって、森や自分たちの暮らしがどう変化していくかということがわかるようになっています。ターンは5年ずつ4ターン。つまり20年後の自分たちの未来をシミュレーションしてもらいます。
実際に森に行ってみたくなるゲーム

実際の住宅メーカーの方に体験してもらうなど、現場の意見も取り入れてゲームをブラッシュアップさせていきました。小学校高学年から楽しんでもらえます。リリース前に体験会を行ったんですが、「森を考えるきっかけになった」「木を切らなければいいと誤解していた」という感想の他に、「森に行きたくなった」「木で何かつくってみたくなった」という子どもたちの声が多かったのも嬉しかったです。森の問題は、全国いろいろなところで起こっています。このゲームを学習ツールとして使ってもらえるように、講師の養成もはじめています。学校はもちろんですが、森の仕事に携わっている人たちにもぜひ体験していただきたいです。
山梨日日新聞社 「moritomirai(森と未来)」事務局 藤井 聖二さん


この取り組みのSDGsを知ろう
「すぐわかるSDGs」では、SDGsの17の目標をイラスト付きで分かりやすく解説しています。気になるゴールを押すと、目標の解説を1分程度で読むことができます。この記事に登場したSDGsを見てみましょう。

Brother presents Music Earth
今、世界では温暖化、貧困、格差社会…様々な地球規模の課題があります。
これからの「地球」の為に、今、私たちにできる事は一体何なのでしょうか?

毎週月曜 19:30 -19:55
FM AICHIにて放送中