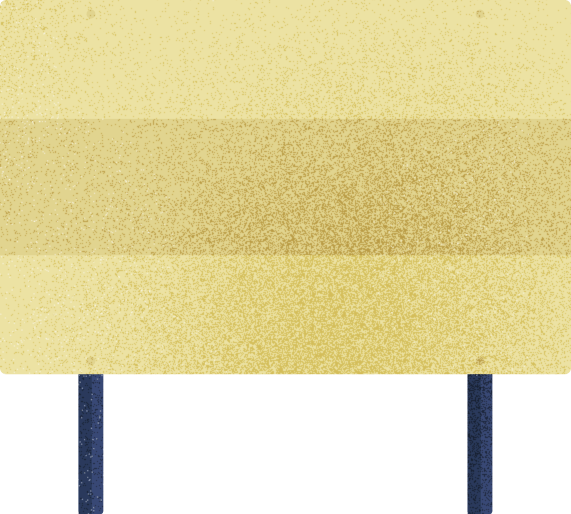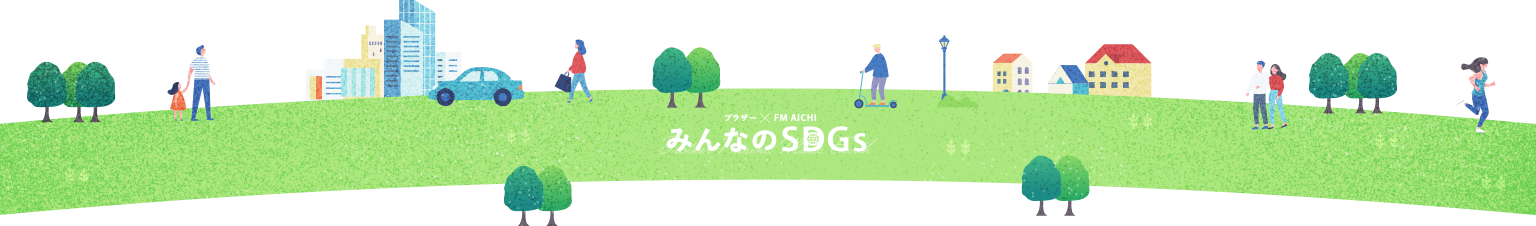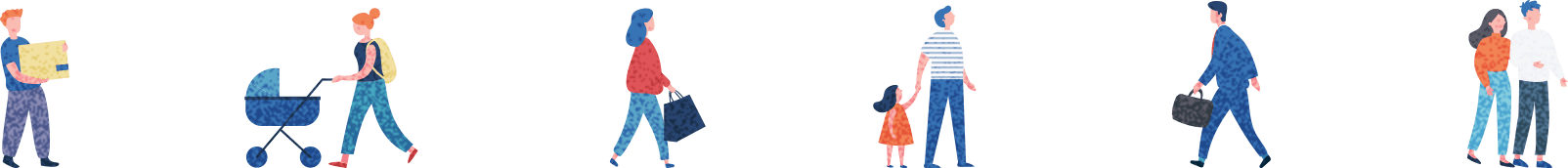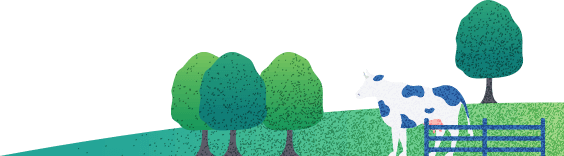前回、入院した子どもや付き添いをする家族のサポートをするため、全国のNPO団体が発起人となって始めた「小児病棟付き添い食支援連絡会えんたく」についてお話をうかがいました(1月30日放送内容参照)。愛知県で活動する「小児がんファミリーピアサポーター 和樂~waraku~」はその発起団体のひとつ。代表の伊藤 麻衣さんに活動の内容についてお話をうかがいました。
「同じ経験をした仲間の視点」で応援

小児がんの子どもと家族を「ピア」(同じ経験をした仲間)の視点で応援する活動を愛知県内で行っています。入院したときってすごく孤立感、孤独感におしつぶされそうになるんですね。同じ経験をした仲間がいることで、「大丈夫だよ」とか「つらいって言っていいんだよ」っていう言葉が届くといいなと思っています。
「和樂」は、立ち上げメンバーの私と副代表、 それぞれの子どもの名前の漢字をとりました。小児がんにかかわらず、長期入院をしている子どもたちとそのご家族が少しでも笑顔になれるよう、「和やかな場」、「楽しい時」をつくれるようにという意味もこめています。
現在、名古屋第一赤十字病院や名古屋医療センターでお世話になった母親3名がメインメンバー。また活動に賛同してくれる地域のボランティアやサポーターが20名ほど参加してくれています。2020年7月から活動をスタートしたばかりです。
レモネードスタンド=小児がん、はアメリカから

具体的には、ベッド上で遊べるようなおもちゃのキットのプレゼントや「えんたく」で今一緒にとりくんでいる、付き添い家族へのお弁当のお届けなどで直接的な支援をしています(入院中の小児の家族への食事のサポートの現状については、 1月30日放送の内容をご参照ください)。また、レモネードスタンドの運営やチャリティーバザーへの出店を通して、地域の方にも小児がんのことを知ってもらうための活動もしています。 アメリカでは、夏休みの子どもたちの風習に、「レモネードスタンド」があるんですが、小児がんのアレックスちゃんという女の子が、亡くなっていく小児がんの友達たちのために何かできることはないかと考え、「レモネードスタンドなら自分でもできる」と始めたことがきっかけで、今では大きな基金になっています。そのためアメリカでは、「小児がん=レモネードスタンド」というイメージがあります。日本でも親の会が全国展開していて、私たちもそれにのっとって活動しています。和樂の場合、レモネードを1杯ご購入いただくと、だいたい0.5人分のお弁当代になります。
治療後に受け入れる地域の理解も大切

(右)伊藤 麻衣さん
ピアサポート以外の活動として、「地域づくり」にも力を入れています。治療が終わって退院したらそれで終わり、ではありません。中でも「復学」は大きな課題です。体力が回復した状態で退院してくるわけではありません。本人だけではなく、ご家族、兄弟もなかなか学校になじめないということも多いです。子どもたちは入院という特殊な環境の中で成長、発達していくわけですから、そういった問題を地域の方たちに知っていただくこと、またそういう家族が近くにいたらやさしく声をかけられるような場所になってもらえたらうれしいです。そのために、行政、福祉、学校などのつながりをつくり、みなさんに小児がんを知っていただくための「場」づくりをしています。また、サポーターを希望してくださる方の育成や他の団体との交流、年間を通してさまざまな講座を受講するなど、お話を聴くためのスキルアップも必要だと考えています。
小児がんファミリーピアサポーター 和樂~waraku~ 代表 伊藤 麻衣さん


この取り組みのSDGsを知ろう
「すぐわかるSDGs」では、SDGsの17の目標をイラスト付きで分かりやすく解説しています。気になるゴールを押すと、目標の解説を1分程度で読むことができます。この記事に登場したSDGsを見てみましょう。

Brother presents Music Earth
今、世界では温暖化、貧困、格差社会…様々な地球規模の課題があります。
これからの「地球」の為に、今、私たちにできる事は一体何なのでしょうか?

毎週月曜 19:30 -19:55
FM AICHIにて放送中