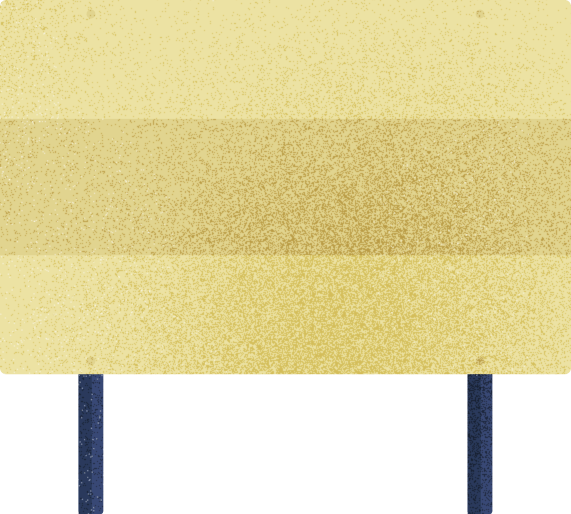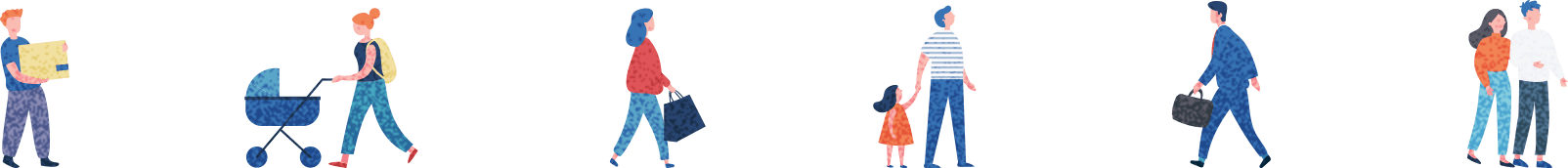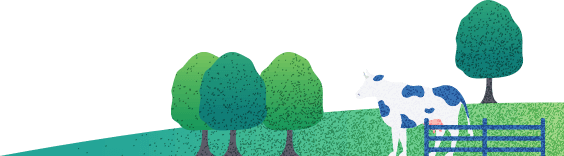2024.06.14
小児病棟での付き添い食を当たり前の光景に
2024.06.14


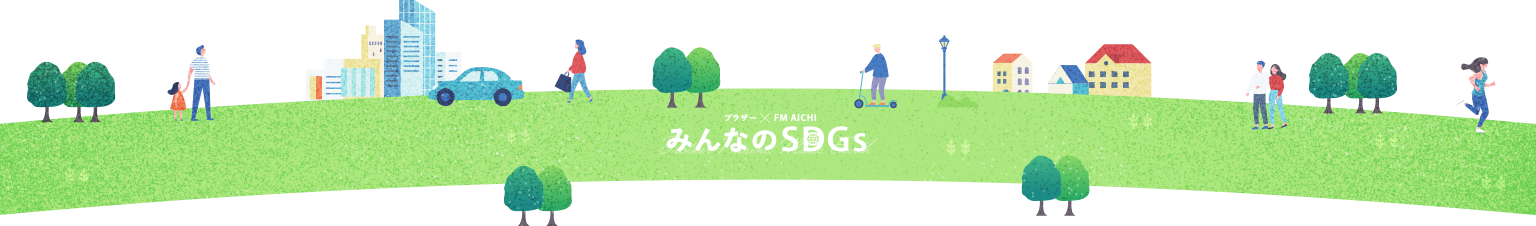
まだ小さな子どもが入院すると、家族は付き添いとして病室に泊まりこんだり、家族の滞在施設から通ったりしながら看病を続けることになります。しかし、こうした付き添いは「病人」ではないため、食事などのサポートがほとんどありません。そんな現状を変えていこうと昨年秋に設立されたのが「小児病棟付き添い食支援連絡会 えんたく」。 発起団体のひとつ、NPO法人 キープ・ママ・スマイリングの理事で、同連絡会の事務局でもある渡辺 千鶴さんに詳しいお話をうかがいました。
小児病棟での親のつきそいの現状

渡辺 千鶴さん
一般の方は、「子どもの入院に付き添っている親御さんがいる」ということもご存知ないかもしれません。入院中に行われる患者さんの世話やケアは看護職の仕事とされていて、日本の病院では家族の付き添いは「原則不要」なんですね。ただし、治療に対する理解が困難な子どもや障害者の人などは、医師が許可すれば付き添うことが認められています。子どもが心細い思いをせず、安心して治療を受けられるよう親の付き添いが求められることも多いように思います。一方で、付き添う側の環境は整っていません。わたしたちキープ・ママ・スマイリングで、入院中の子どもに付き添うご家族を対象に大規模な生活実態調査を行ったところ(2022年11月~12月)、病室に泊まり込んでいた3282人のうち、病院から定期的な食事サービスが「ない」と回答した人が8割以上を占め、病院からの定期的な食事サービスを望んでいる人は9割弱にも上りました。
付き添い食導入への壁

付き添っている親は病人ではないので、医療保険の対象になりません。ですから、食事をはじめ、親の生活サービスを整える財源を病院が確保しにくいんです。それならわたしたちのような患者・家族支援団体からの食支援を受け入れてもらえればと思うんですが、病院側としては食中毒が発生した際の責任の所在など、医療安全面から受け入れに対して消極的です。また、病院が患者・家族支援団体とうまくつながれないこともネックになっていました。わたしたちは、各方面からさまざまな相談を受ける中で、食支援活動は付き添いの親の生活課題を解決する重要な手段の一つであり、貴重な社会資源の一つであると強く感じるようになりました。この大事な役割について医療機関や社会の賛同を得るためにも、付き添い食支援に取り組む団体が「連絡会」という形で「一つにまとまること」が必要だと思いました。
えんたく(丸いテーブル)という名称に込めた思い

キープ・ママ・スマイリングが各地で活動する患者・家族支援団体10団体に声をかけ、賛同を得て「小児病棟付き添い食支援連絡会 えんたく」を設立しました。「えんたく」には、非日常がつづく小児病棟でも、おいしいごはんの差し入れで親御さんが病気のお子さんと同じ食卓を囲み、そこに笑顔が生まれてほしいという願いが込められています。
キャッチフレーズは、「小児病棟で付き添い食が出ることを当たり前の光景に」。まずは2023年12月から半年にわたり「付き添い食を提供したい人・団体のための運営ノウハウ連続講座」を開講。全国の仲間を増やし、運営ノウハウを共有することによって各団体の活動の質向上を目指しています。キープ・ママ・スマイリングが運営する「つきそい応援団」というポータルサイトに、えんたくの連続講座の申込みフォームが掲載されています(2024年6月で終了しました)。設立したばかりのヨチヨチ歩きの連絡会ですが、小児病棟で付き添い食を普及するためのプラットホームになれるよう頑張りますので、ぜひご注目ください。
NPO法人 キープ・ママ・スマイリング
所在地:東京都中央区銀座4-13-19 銀林ビル4F
連絡先: こちら
公式サイト: http://momsmile.jp/
小児病棟付き添い食支援連絡会 えんたく事務局(NPO法人 キープ・ママ・スマイリング 理事) 渡辺 千鶴さん


この取り組みのSDGsを知ろう
「すぐわかるSDGs」では、SDGsの17の目標をイラスト付きで分かりやすく解説しています。気になるゴールを押すと、目標の解説を1分程度で読むことができます。この記事に登場したSDGsを見てみましょう。

Brother presents Music Earth
今、世界では温暖化、貧困、格差社会…様々な地球規模の課題があります。
これからの「地球」の為に、今、私たちにできる事は一体何なのでしょうか?

毎週月曜 19:30 -19:55
FM AICHIにて放送中