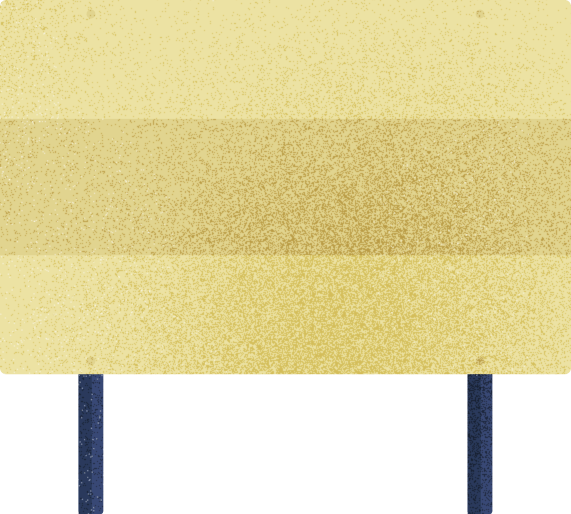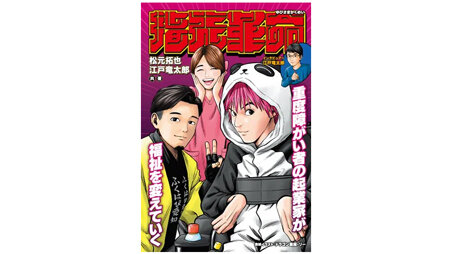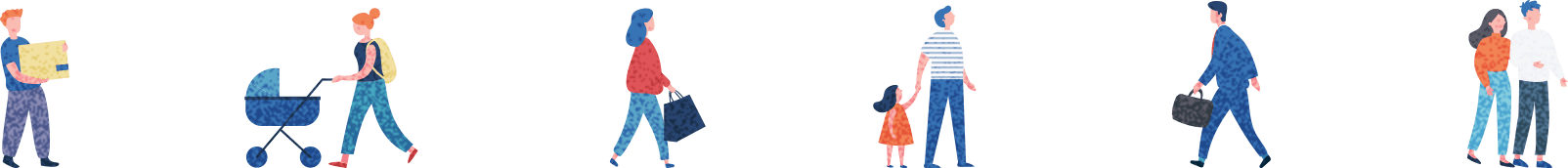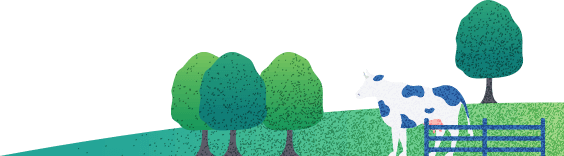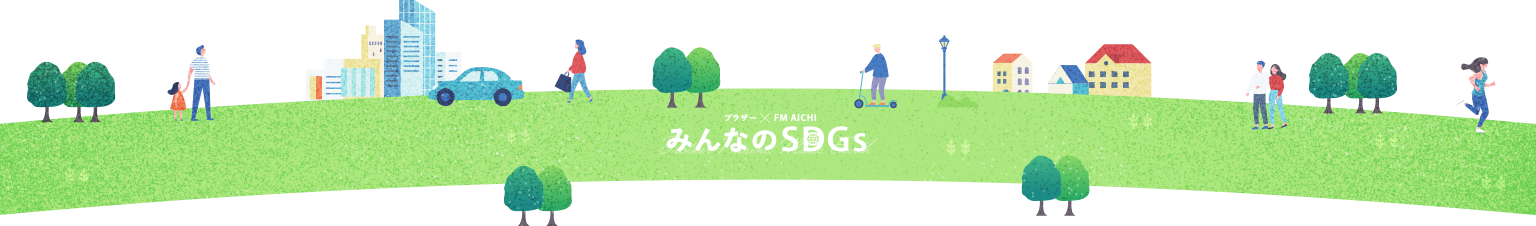
番組では月に一度、東山動植物園で飼育している「絶滅危惧種」にスポットを当てて紹介していますが、今年最初のテーマは、今年の干支「ヘビ」。
名古屋市内に生息するヘビたちの生態について、東山動植物園 飼育第二グループ 藤谷 武史さんにお話をうかがいました。
名古屋市内に生息する8種類のヘビのうち6種が絶滅危惧種

シマヘビ(写真提供:名古屋市東山動植物園)
名古屋には一般的な種であるシマヘビ、アオダイショウ、ジムグリ、ヤマカガシ、マムシ、ヒバカリ、その他確認はされているものの、その例は極めて少ないタカチホヘビやシロマダラの合計8種類のヘビが生息しています。
名古屋市は独自に「名古屋市版レッドリスト」を作成しているんですが(2020年が最新版)、それによるとこの中の6種類が絶滅危惧種、もしくは準絶滅危惧種に指定されており、ジムグリ、シロマダラは絶滅危惧ⅠB類、ヒバカリ、ヤマカガシ、ニホンマムシは絶滅危惧Ⅱ類、シマヘビは準絶滅危惧種です。ちなみにタカチホヘビは「情報不足」というカテゴリー。
名古屋に生息しているヘビの中で絶滅危惧種に指定されていない種は、タカチホヘビを除いてアオダイショウたった1種なんです。
ヒバカリの名前の由来は「噛まれたらその日ばかりの命」

藤谷 武史さん(写真提供:名古屋市東山動植物園)
東山動植物園では、シマヘビとヒバカリを飼育しています。ヒバカリは、全長40センチ~60センチの小型のヘビ。本州、四国、九州と、その周辺の島々に生息する日本固有亜種です。その名前は、「嚙まれたらその日ばかりの命」から付いたとされていますが、実際には毒は持っていないとされていますし、捕獲してもあまり噛むことはありません。
身体の色は淡褐色や褐色をしていて、鼻の先から口角、首にかけて薄い黄色か白い筋状の斑紋があるのが特徴です。エサはカエルやオタマジャクシ、小魚、ミミズなど。魚などを水中で獲るために浅い水中に潜るのも得意です。水田地帯や丘陵地などに生息しています。
絶滅が危惧されるほど減った原因として一番考えられるのは、ヒバカリのエサであるカエルの減少です。ヒバカリは毒を持っているとされるアズマヒキガエルのオタマジャクシを食べるのですが、名古屋市内のアズマヒキガエルの繁殖期は2月下旬から3月。4月初旬に冬眠から覚めたヒバカリがこれらを食べるために水辺にやってきても、近年アズマヒキガエルが激減しているため非常に厳しい状況です。同じころに産卵がある二ホンアカガエルも同様です。
名古屋市内に生息する両生類のおよそ8割が絶滅の危機

シマヘビ(写真提供:名古屋市東山動植物園)
ヤマカガシやニホンマムシ、シマヘビなどもカエルを捕食するヘビです。ヒバカリはもちろんですが、こうしたヘビたちもまたカエルの減少によるエサ不足が、彼らの数を減らしている原因のひとつと考えられます。生き物は、食べる、食べられるの関係、つまり食物連鎖が絡み合って生きています。そのため、ひとつの生き物の減少が関連する様々な生き物に影響を与えてしまうというわけです。ちなみに、私は名古屋のレッドリストの「両生類」の専門委員も務めているんですが、名古屋に生息する両生類(イモリやサンショウウオなど含む)のおよそ8割が絶滅危惧種に指定されています。
施設名:名古屋市東山動植物園
所在地:〒464-0804 愛知県名古屋市千種区東山元町3-70
電話:052-782-2111
公式サイト:www.higashiyama.city.nagoya.jp
Youtubeチャンネル:www.youtube.com/user/HigashiyamaPark
開園時間:9:00~16:50(入園は16:30まで)
休園日:月曜日(祝日の場合は直後の平日)、12/29~1/1
東山動植物園 飼育第二グループ 藤谷 武史さん


この取り組みのSDGsを知ろう
「すぐわかるSDGs」では、SDGsの17の目標をイラスト付きで分かりやすく解説しています。気になるゴールを押すと、目標の解説を1分程度で読むことができます。この記事に登場したSDGsを見てみましょう。

Brother presents Music Earth
今、世界では温暖化、貧困、格差社会…様々な地球規模の課題があります。
これからの「地球」の為に、今、私たちにできる事は一体何なのでしょうか?

毎週月曜 19:30 -19:55
FM AICHIにて放送中