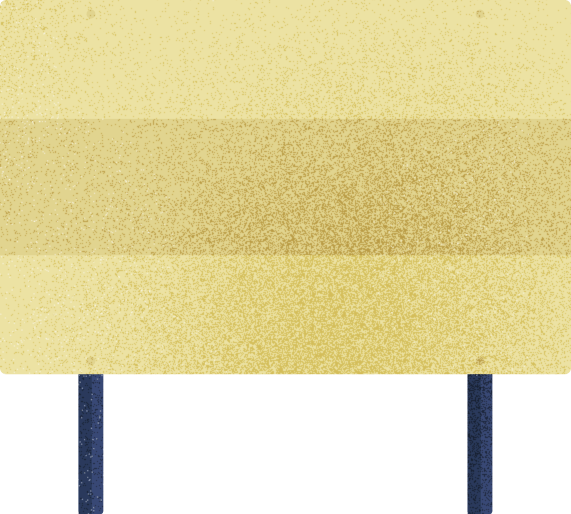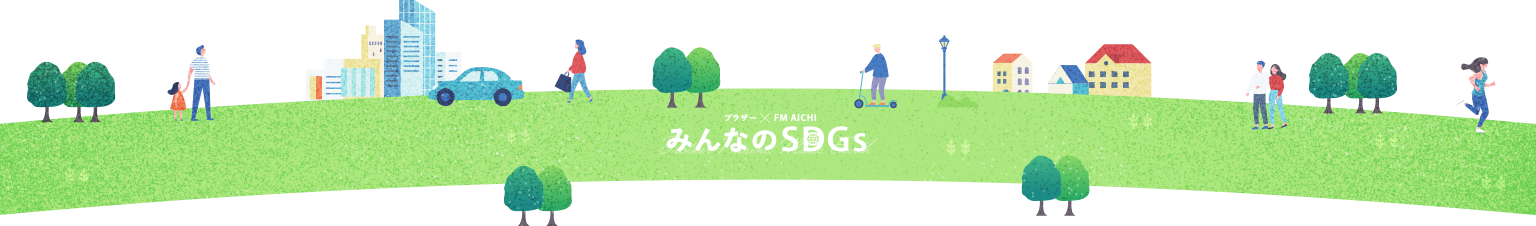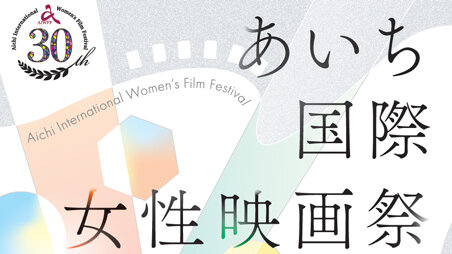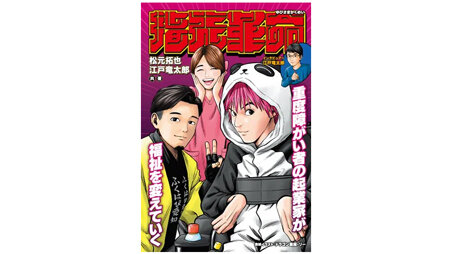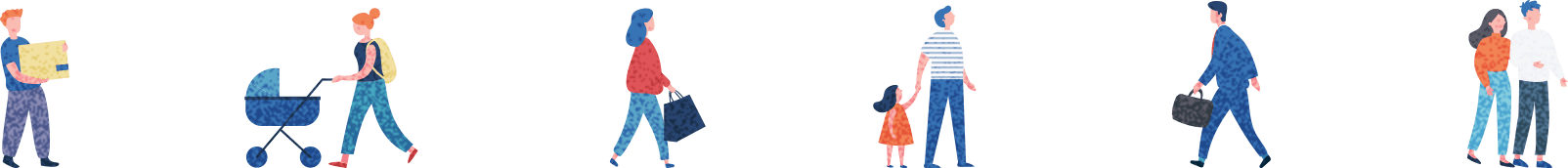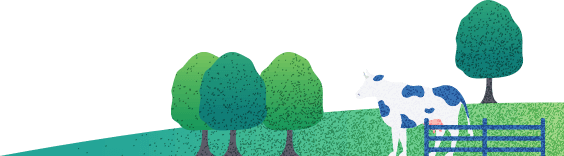「ゴミ拾いはスポーツだ」を合言葉に、チーム対抗のごみ拾いを楽しむ「スポGOMI」。
2008年に日本で生まれたスポーツで、番組では以前、この「スポGOMI」を考案し、活動を広めている日本スポGOMI連盟の代表 馬見塚(まみつか) 健一さんに、活動の内容や活動を始めたきっかけなどを伺いました。
そして、その後なんと初めての「スポGOMI」のワールドカップが開かれたんだそうです。今日は、世界に広がる「スポGOMI」について改めてうかがいます。
合言葉は「ゴミ拾いはスポーツだ!」

小さいお子さんから高齢者まで、スポーツの得意不得意関係なく競っていただけるようにしたかったので、ルールは、①走らないこと、② 3~5名でチームを組んで、エントリーしていただくこと(世界大会は 3人1組)、③競技をするときは、指定のトング(安全性が高くてゴミを拾いやすいものを新潟の燕三条で製作)を使うことです。制限時間は1時間。得点は重量などで競わず(そうすると若くて元気な人たちが有利になる)、例えば、たばこの吸いがらなどは目線の低い子どもが有利なので、ポイントを高くするなど、試行錯誤しながらルールを決めました。
これまでに国内外で延べ16万人の方が参加してくださっています。「ゴミ拾いもスポーツになるんだね」とか、「きれいだと思ってた町にも、思った以上にゴミが落ちてるんだなあ」といった感想をよく聞きます。
初のワールドカップ開催に意外な苦労

いずれはスポGOMIの世界大会をやってみたいという、ぼんやりとした思いはありました。2008年から活動して、こんなに早く実現できるとは思わず、感謝しかないです。
2023年に第1回目の世界大会を開催し、日本を含めて21か国が参加しました。優勝はイギリスチームで、日本代表は新潟のチームだったんですが、準優勝でした。自国開催だったので、日本チームは悔しがっていましたね。
日本では「ゴミ拾い」を誰もがやったことがあると思うんですが、海外の方たちの中には、ゴミ拾い自体やったことがない方もいて、さらにそれを「スポーツとして楽しむ」というスポGOMIのコンセプトを伝えることに非常に苦労しました。欧米などでは、ゴミを拾うことを職業にしている方もいて、スポGOMIでゴミを拾ってしまうとその人たちの仕事を奪うことになると、行政からストップがかかったこともありました。文化や習慣の違いからの難しさもいろいろ感じました。
第2回「スポGOMIワールドカップ」開催へ

馬見塚 健一さん
スポGOMIを通して国際交流できたことはとてもよかったですし、優勝したイギリスチームは、自国に帰ってスポGOMIの普及に尽力してくれています。第2回目になる2025年の大会は、34~35か国の参加になる予定です。第1回目の大会がそれぞれの国で話題になり、開催後に近隣の国から「次やるときはうちの国でやってくれないか」という問い合わせがかなりありました。
日本代表を決める国内予選の大会はもうスタートしています。愛知県はすでに10月に、岐阜県は12月に開催されました。今年の大会では、活動を理解して賛同してくれた各国のオーガナイザー(スポGOMIのイベントや大会を企画・運営する組織や団体)としっかり連携を深めて、スポGOMIがワールドカップ以外でもそれぞれの国で広がっていくよう、注力していきたいと思っています。
日本スポGOMI連盟 代表 馬見塚 健一さん


この取り組みのSDGsを知ろう
「すぐわかるSDGs」では、SDGsの17の目標をイラスト付きで分かりやすく解説しています。気になるゴールを押すと、目標の解説を1分程度で読むことができます。この記事に登場したSDGsを見てみましょう。

Brother presents Music Earth
今、世界では温暖化、貧困、格差社会…様々な地球規模の課題があります。
これからの「地球」の為に、今、私たちにできる事は一体何なのでしょうか?

毎週月曜 19:30 -19:55
FM AICHIにて放送中