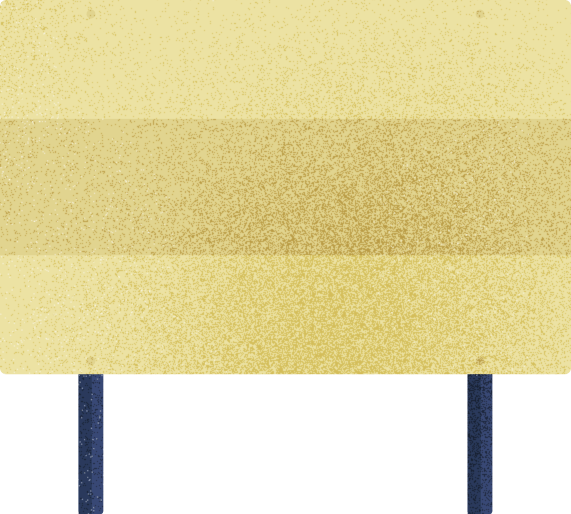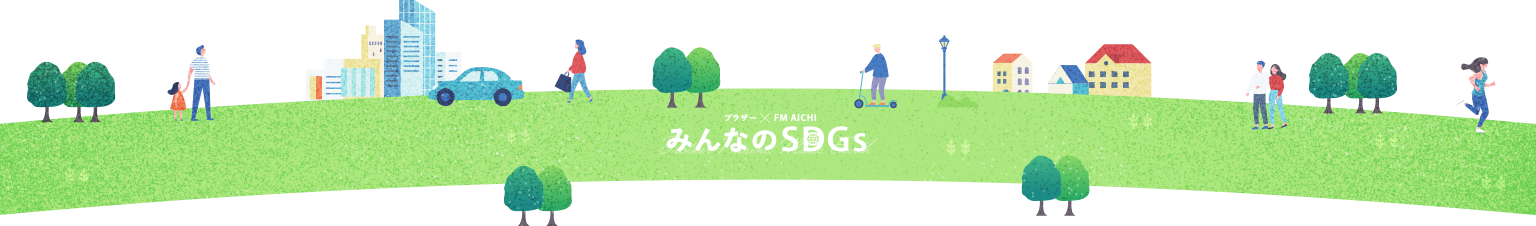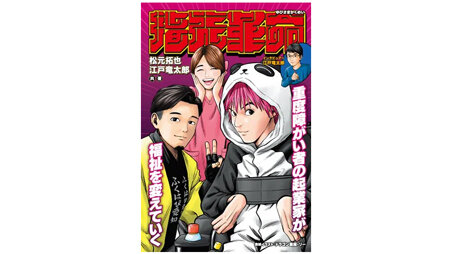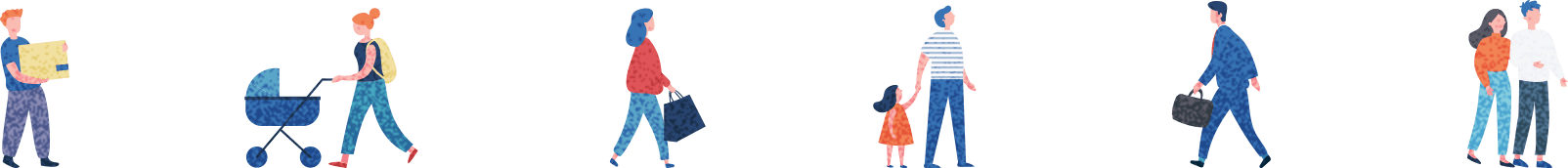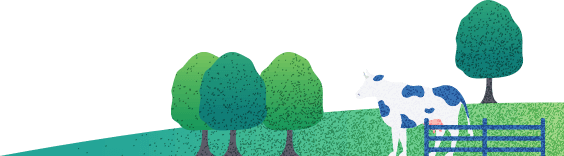1995年の阪神淡路大地震、2004年の新潟県中越地震、2011年の東日本大震災、2024年の能登半島地震…。日本では実に多くの地震が発生しています。そして、いつか起こるといわれている南海トラフ地震。日本で暮らす以上、地震という自然災害を避けては通れません。一人ひとりが考え、どんな備えができるのか。
親子向けの防災イベントなどを企画し、備えの大切さを情報発信している地域の団体、「防災ママかきつばた」の代表 高木 香津恵さんにスタジオにお越しいただきお話をうかがいました。
全ての親子たちに「備える大切さ」を伝えたい

小学校での防災講座
「防災ママかきつばた」は、愛知県の知立市、刈谷市、名古屋市、碧南市、安城市などのパパ、ママたちで結成する防災団体です。ここ数年で県外のメンバーも増え、現在42名で活動しています。主に防災セミナーの企画や親子向けの情報発信などを行っていて、昨年末も「名古屋市内南海トラフ地震を乗り越える方策を考える講演会」で、名古屋大学の福和 伸夫先生たちと一緒に講演を行いました。
阪神淡路大震災のとき、私は小学3年生でした。京都に住んでいたんですが、京都も震度5を記録。あのときの揺れの怖さは忘れられません。大人になり、ママになってからも防災の大切さは感じていたものの、日々の子育てで精一杯で、なかなか「備える」ことができていませんでした。しかし、名古屋で開催された親子の防災講座「防災ママカフェ」に参加し、東日本大震災で被災されたママたちの話を聞いて、「今のままでは、子どもを守るどころか、自分さえも守れない」と気づいたのが、団体を立ち上げるきっかけでした。
避難場所の確認は、家族間でより具体的に

まずはハザードマップをチェックして、住んでいる地域で「何が起きるのか」を知ることが大切。さらに家族が通っている学校や会社などの周辺についても調べておいていただきたいと思います。紙のハザードマップだけだと、表示されていない部分もあるので、ぜひWebでも。「重ねるハザードマップ」(国土地理院)でチェックしておいてください。
また、避難所の確認も必要です。いざ避難することになると大勢の人がそこに集まることになりますので、例えば学校の校庭が指定されているとしたら、「お昼の12時40分~13時までの間に二宮金次郎の前にいるよ」など、具体的な時間と場所を家族で事前に決めておくことをオススメします。家の中での備えは、家具の固定などはもちろんですが、一番大切なのは「部屋を片づけておくこと」。片づいていないと、物が落ちてきたり進路を妨げられたりして、それだけでけがをする確率が高くなります。
防災リュックは家族一人ひとり・背負ってみること

高木 香津恵さん
防災リュックを用意している方は増えていると思いますが、家族でひとつだけというケースも多いようです。ぜひ、家族一人ひとり、自分の防災リュックを用意していただきたいと思います。そして必ず背負ってみてください。私自身の失敗談でもありますが、大きな登山リュックにこれでもかと詰めすぎたことがあって…(笑)。リュックを背負って、お子さんを連れて足場の悪い中を避難所まで移動することを考えておかないといけないです。せっかく用意しても「使えない備え」にならないように。
そして、普段出かけるときに持っておくと安心なのが「防災ポーチ」です。個人個人で持ち物は変わると思いますが、私は小さな羊羹(常温で長期保存できる携帯食として)と携帯トイレ(ティッシュや防臭袋と一緒に)は必ず入れています。他にオススメは、手のひらサイズのレインポンチョ(急な雨対策としてはもちろん防寒にもなる)。常備薬などがある方はそれらもぜひ入れておいてください。
防災ママかきつばた 代表 高木 香津恵さん


この取り組みのSDGsを知ろう
「すぐわかるSDGs」では、SDGsの17の目標をイラスト付きで分かりやすく解説しています。気になるゴールを押すと、目標の解説を1分程度で読むことができます。この記事に登場したSDGsを見てみましょう。

Brother presents Music Earth
今、世界では温暖化、貧困、格差社会…様々な地球規模の課題があります。
これからの「地球」の為に、今、私たちにできる事は一体何なのでしょうか?

毎週月曜 19:30 -19:55
FM AICHIにて放送中