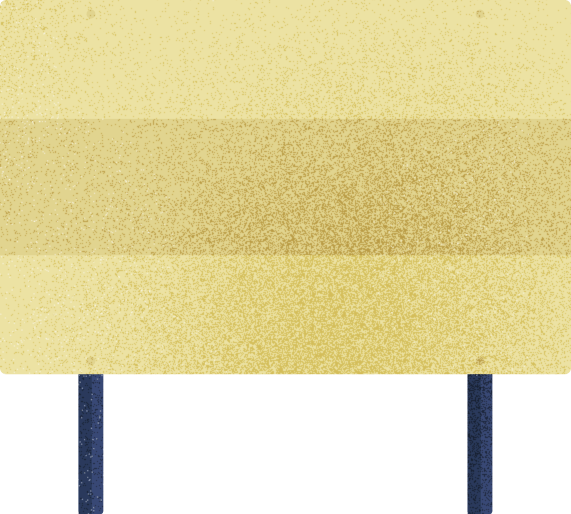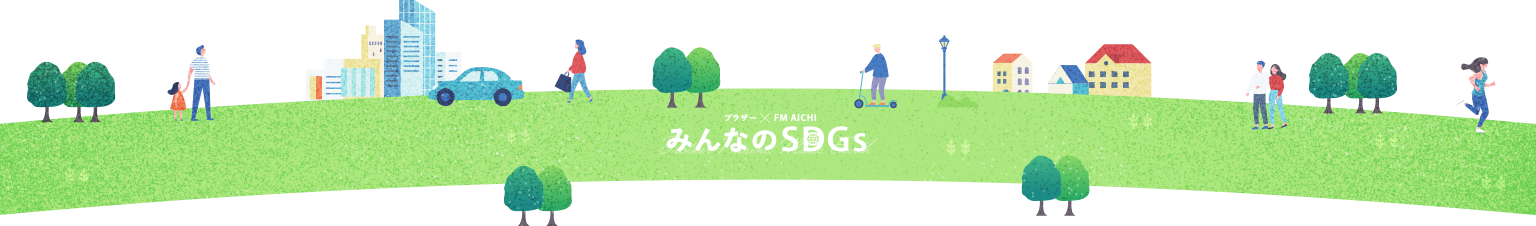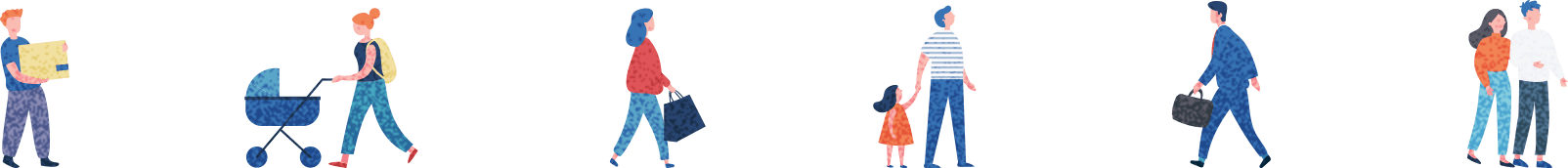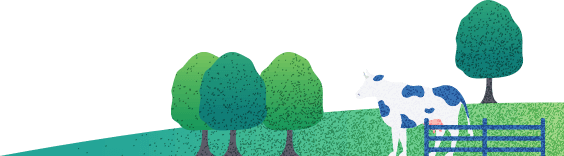「なごや環境大学」ってご存じでしょうか?市民団体や企業など、さまざまな立場から知識や経験をもちよって環境やSDGsに関する幅広い学びを行う環境学習のネットワークです。「大学」と名前はついていますが、実際に校舎があるわけではなく、「まちじゅうがキャンパス」をキーワードにさまざまな講座を企画しています。
環境教育コーディネーターの岸 晃大(こうだい)さんにスタジオにお越しいただきお話を伺いました。
まちじゅうがキャンパス、入学資格はエコ・ゴコロだけ

愛岐の里山探検隊 田植え体験
「環境に関することなら何でも学べる」ところで、「まちじゅうがキャンパス」「入学資格はエコ・ゴコロだけ」をキーワードに、さまざまな場所で講座が展開されています。
講座の内容は、前期と後期にわけて発行するガイドブックに掲載されていますが、今年の前期は64講座。近くの公園や企業の工場など、さまざまな場所で開かれます。テーマは、わたしたちの身近な暮らしから、地球の気候変動、自然との共生、国際協力まで多岐にわたります。
例えば、長く続いている事務局主催のイベントで、「愛岐の里山探検隊」があります。名古屋市のゴミの最終処分場は岐阜県多治見市にあるんですが、地元の方々の協力で豊かな里山が保たれています。ここに名古屋市の小中学生がお子さんだけで参加するという講座です。田植えや芋ほりの体験のほか、自分たちが普段出したゴミがどうなっているのかを学びます。
また、現在は名古屋市が市の事業として行っていますが、「カイボリ」(池の水を全部抜いてたまった泥を排出したり、外来種を駆除したりする)の講座も当初ありました。「カイボリ」の重要性を訴えるものとして、その先駆けになったと言えます。
きっかけは藤前干潟の埋め立て問題

名古屋の人々の環境への関心が高まったのが、藤前干潟の埋め立て問題(1981年に藤前干潟をごみの埋立処分場にする計画が発表され、渡り鳥をはじめとする生き物の宝庫、藤前干潟を守りたいとの市民の声が高まった)から始まった「ごみ非常事態宣言」でした。市民と企業と行政が共同でゴミ分別に取り組み、大幅にゴミを減らして干潟を守ったという歴史があります。
さらに20年前、2005年の愛知万博が「自然の叡智」をテーマに開催され、この地方の環境に対する意識がさらに高まりました。この高まりを一過性で終わらせるのではなく、平時にも定着させようと始まったのが、「なごや環境大学」でした。この「なごや環境大学」のしくみは、全国に先駆けた先進的な取り組みだったと聞いています。
今年で20周年、その先へ!

岸 晃大さん
「なごや環境大学」がスタートして今年で20年。2024年までに合計2800もの講座が開かれています。当初174団体に協力をいただいていたのが、今では526団体と大幅に増えました。
しかし、この環境大学だけではなく、環境問題全般について懸念があります。特に若い人たちの中で、環境問題に関心のある人とそうでない人とが二極化しているということです。最近の酷暑、洪水や大雪などの異常気象が続き、気候変動が目に見えているので、環境問題の重要性への意識はあるとは思うのですが、20年前の愛知万博の頃に比べて、関心が薄れているような気がします。とはいえ、SDGsの目標達成は2030年。私たちなごや環境大学でできることとして、20周年を機に、改めて名古屋の環境について、より皆さんに行動にうつしていただけるような講座をコーディネートできたらと考えています。記念のイベントも企画中ですので、楽しみにしていただけたらと思います。
環境教育コーディネーター 岸 晃大さん


この取り組みのSDGsを知ろう
「すぐわかるSDGs」では、SDGsの17の目標をイラスト付きで分かりやすく解説しています。気になるゴールを押すと、目標の解説を1分程度で読むことができます。この記事に登場したSDGsを見てみましょう。

Brother presents Music Earth
今、世界では温暖化、貧困、格差社会…様々な地球規模の課題があります。
これからの「地球」の為に、今、私たちにできる事は一体何なのでしょうか?

毎週月曜 19:30 -19:55
FM AICHIにて放送中