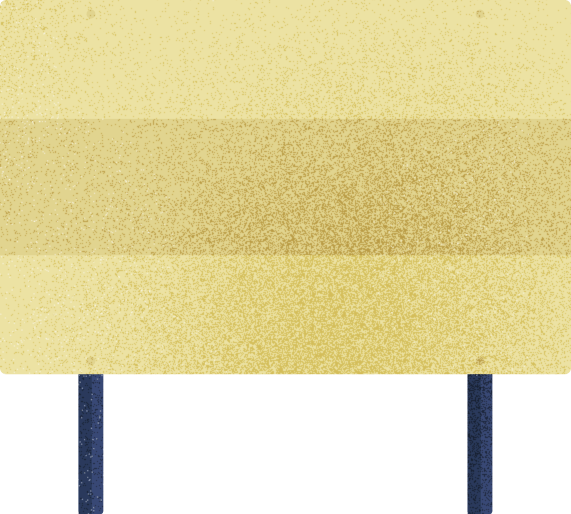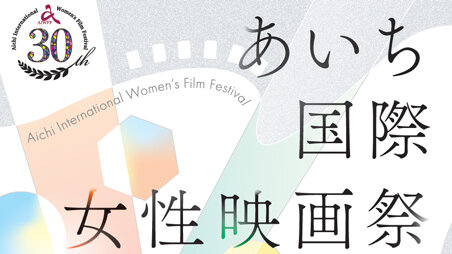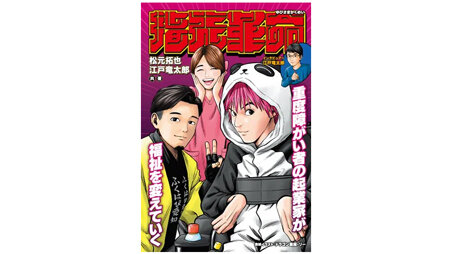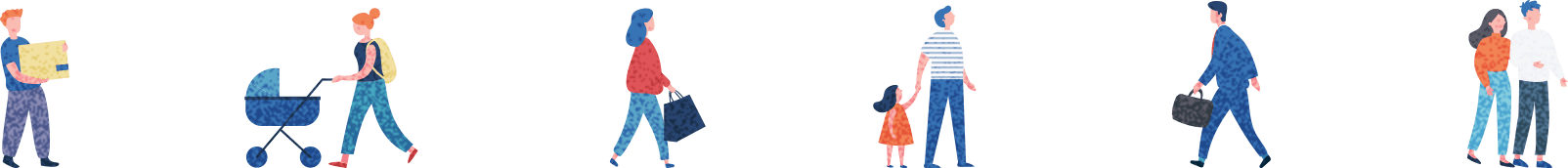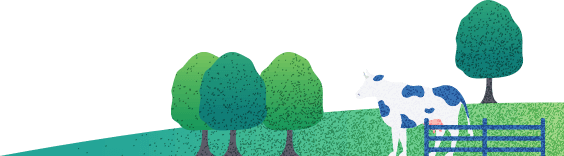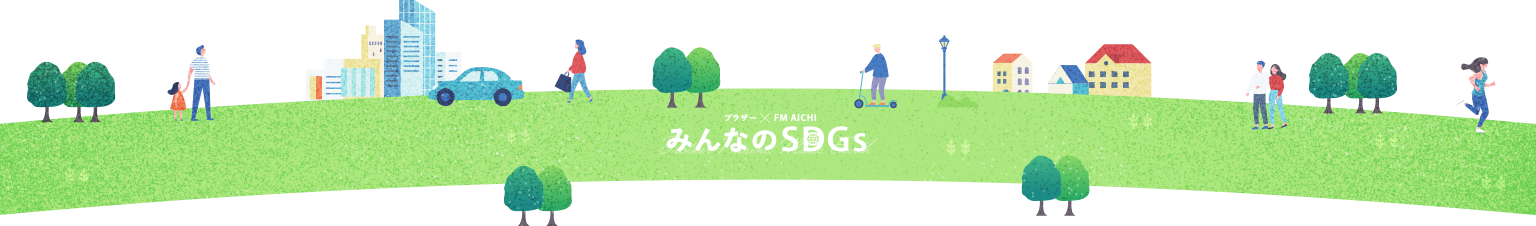
サッカーのワールドカップやメジャーリーグの球場で、試合後に日本人サポーター達がゴミを拾って帰る様子が、海外からの賞賛を集めました。そんな「ゴミを拾う」という行為をスポーツにして、楽しみながら社会貢献しよう!という活動があります。
その名も「スポGOMI」。日本スポGOMI連盟代表 馬見塚 健一さんに「スポGOMI」誕生のきっかけやルールについてお話を伺いました。
「スポGOMI」誕生のきっかけ

横浜に住んでいた時、日課にしていた「朝ラン」が発想のきっかけ。ランニングの途中で目にするゴミがだんだん気になってきたんです。せめて、自分のランニングのルートだけでも、きれいにしたいなという気持ちがわいてきて、自然にゴミ拾いを始めました。
でも、ゴミを拾っていると、ちゃんと走れない(笑)だから、なんとか走りながらゴミを拾う方法はないものかと工夫するようになったんです。例えば、ひとつゴミを拾ったあと、次に10m先にあるペットボトルはスピードを落とさないように拾ってみようかな。その次は大腿筋を意識してみようかな。とかね。そんなことをしているうちに、だんだんゴミがターゲットになっていったんです。「これ、まさにスポーツだな」と。既存のゴミ拾いにスポーツ的な要素を設けることで、いろんな人が参加でき、ゴミ拾い自体も楽しくなるのではと考えました。
「スポGOMI」のルール

僕のランニングから始まった「スポGOMI」ですが、最初に決めたルールは「走らない」こと。小さいお子さんから高齢者の方まで、誰でも参加できて街中で安全に行うためです。1チーム3名から5名でエントリーしていただき、制限時間は60分。使う道具は指定のトング。大会用に新潟の燕三条でオーダーして作ってもらったもの。これをレンタルして参加してもらいます。
採点は、ゴミの分別ごとにポイントを加算するしくみ。例えば、燃えるゴミは100g・10ポイント、燃えないゴミは100g・5ポイント、ペットボトルなどの資源ごみは100g・120ポイント、特に拾いづらいタバコの吸い殻などは、100g・100ポイントなどなど。目線が低い小さな子どもたちでも一生懸命拾ったら、大人のチームを抜いて上位に入賞できるというような、年齢や体力で差がつかないよう、大会にドラマが生まれるようなルールを試行錯誤しながら発展させてきました。
広がる「スポGOMI」

2008年にスタートした「スポGOMI」。これまで1,100もの大会が開かれ、のべ10万人以上が参加した計算になります。リピーターも多く、自分たちが住む街以外の大会に参加してくれる家族もいます。また、「スポGOMI」を恒例行事にしてくれている自治体や企業も増えました。
参加した人たちから、「ゴミとの向き合い方が変わった」という意見をよく聞きます。
子どもたちも授業などで海洋プラスチックごみの問題を勉強していますが、なかなか「自分ごと」としてとらえるのは難しい。「スポGOMI」に参加することで、自分たちの地域のゴミを目にして、「どうしたらゴミを出さない生活ができるか?」を考えるきっかけになっているのかなと感じています。
ゴミ問題は、地球規模で取り組むべき問題でもあります。今後は日本と違ってゴミを拾う習慣があまりない国(ミャンマー・韓国・パナマ・ベトナムなど)でも開催を予定しています。スポーツという入口からゴミ拾いを体験することで、自分たちの街にこんなにゴミがあったんだ!と驚き、見直すきっかけになればと思っています。
いつか、世の中から「スポGOMI」がなくなることが本当のゴールですね。
日本スポGOMI連盟代表
馬見塚 健一さん


この取り組みのSDGsを知ろう
「すぐわかるSDGs」では、SDGsの17の目標をイラスト付きで分かりやすく解説しています。気になるゴールを押すと、目標の解説を1分程度で読むことができます。この記事に登場したSDGsを見てみましょう。

Brother presents Music Earth
今、世界では温暖化、貧困、格差社会…様々な地球規模の課題があります。
これからの「地球」の為に、今、私たちにできる事は一体何なのでしょうか?

毎週月曜 19:30 -19:55
FM AICHIにて放送中