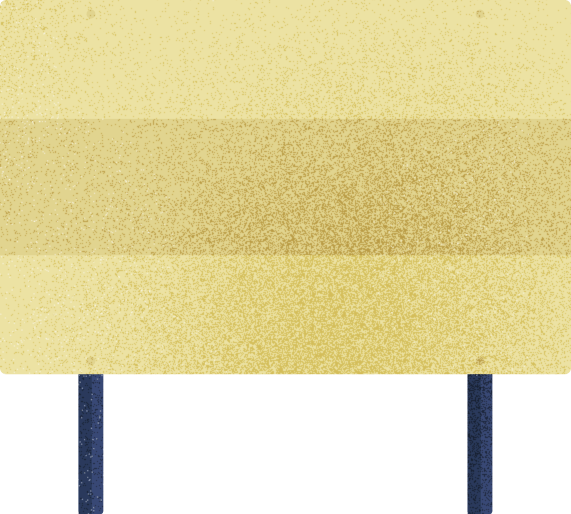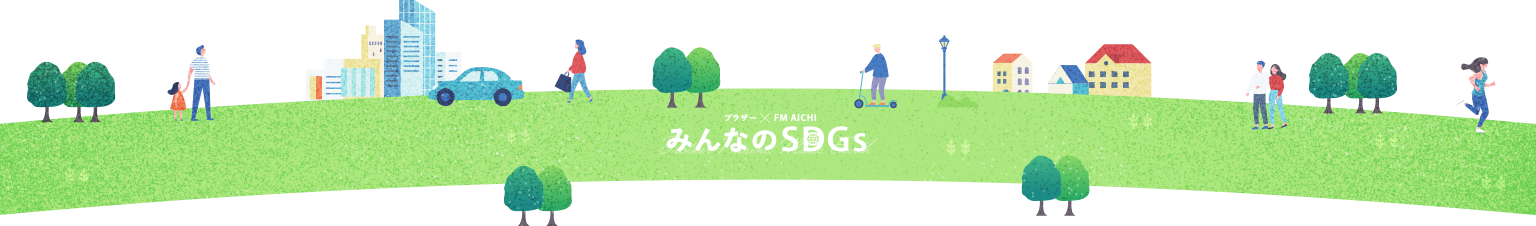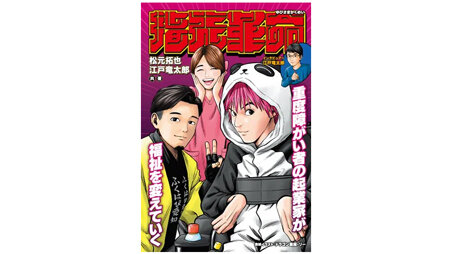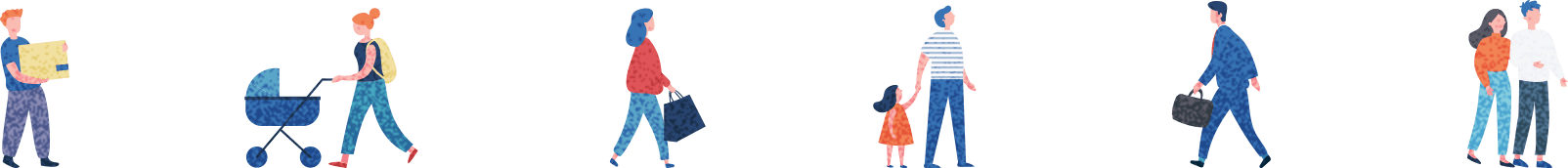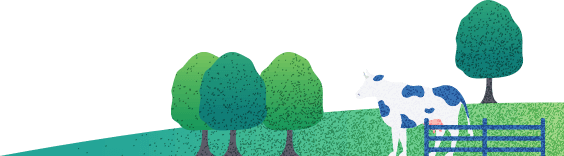以前、名古屋名物のういろの「はしっこ」をういろのパッケージにリサイクルする「ういろペーパー」の取り組みをとりあげました。「名古屋名物から紙をつくる(2023年1月10日放送)」
なんと、今度は、ミニトマトになるというんです。「ういろ」が「ミニトマト」になる、ってどういうことなんでしょうか。
株式会社 大須ういろの村山 賢祐(けんゆう)さんにスタジオにお越しいただき、詳しいお話をうかがいました。
ういろからミニトマトをつくるってどういうこと?

ういろの製造過程で生じる製品の残りかす、つまり食品残渣(ざんさ)であるであるういろのはしっこを紙にリサイクルするという取り組みについて前回お話させていただいたんですが、他にも食品残渣はたくさんあります。
この残渣を活用できないかと始めたのが、「バイオマス資源として再利用して、そのエネルギーからミニトマトを育てる」という取り組みです。これは、愛知県半田市にある株式会社ビオクラシックス半田からさんから提案いただいたのが始まりです。食品残渣を微生物の働きで発酵させてメタンガスを生成し、電気、熱、CO2のエネルギーに変換。このうち、熱とCO2をトマトのハウスに利用して、「HANDAミラトマト」という名前のミニトマトをつくっています。名前もかわいいですが、味もすごく甘くておいしく、ある意味宝石のようなトマトです。
ういろペーパーがつなぐSDGsのご縁

この取り組みを始めたそもそものきっかけは、弊社が2年ほど前にはじめた「ういろの残渣からういろペーパーをつくる」という事業を知った、株式会社ビオクラシックス半田さんの営業の方から「こういう取り組みをしている会社なら話を聞いてくれるんじゃないか」という読みで突然電話がかかってきたことです。「見ている方は見ているんだな」と感じました。
半田市のある知多半島は、しょうゆ、味噌、納豆などを作る食品メーカーもあり、もともと醸造文化の盛んな土地柄。食品残渣は出ますし、また、牛などの畜産も盛んなので、その糞尿なども利用してバイオマス資源として使っていこうという動きがあるんです。種類もいろいろあったほうが、微生物も元気に働くようです。
「やったほうが未来につながるよね」という理念に賛同

(写真中央:村山 賢祐さん)
ういろペーパーに再生できるのは、実際のところ弊社から出る食品残渣の1~2%程度でした。しかし、このミニトマトづくりには、食品残渣のおよそ60%が使用されています。いかに100%に近づけていくかは課題ですが、食品残渣の半分以上がトマトの生育に役立っているといるというのは誇らしく思っています。
こういった取り組みができるかどうかは、やはり企業姿勢でしかないと考えています。何かをしようとすれば、一定のコスト(お金)はかかります。しかし、コストをかけてでもやったほうがいい、社会的に正しいよね、やったほうが楽しい、そして社員も、お客様も、それを知ったときに「ハッピーになれる」ならやるべきかなと。それが経営者としても、企業としても向き合うべき姿勢なのかなと思っています。「やったほうが未来につながるよね」ということは、一緒にやっているみなさんも思われていることで、そんな仲間が増えていくと心強いです。
株式会社 大須ういろ 代表取締役 村山 賢祐さん


この取り組みのSDGsを知ろう
「すぐわかるSDGs」では、SDGsの17の目標をイラスト付きで分かりやすく解説しています。気になるゴールを押すと、目標の解説を1分程度で読むことができます。この記事に登場したSDGsを見てみましょう。

Brother presents Music Earth
今、世界では温暖化、貧困、格差社会…様々な地球規模の課題があります。
これからの「地球」の為に、今、私たちにできる事は一体何なのでしょうか?

毎週月曜 19:30 -19:55
FM AICHIにて放送中